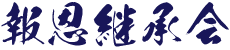ご先祖様の恩を感じ、先祖供養・お墓参りをしましょう
|
一般社団法人 日本生活助力協会 mail:houon@jstm.or.jp |

| ◎お墓の歴史 ◎現在のお墓 ◎お墓を建てる時期 ◎お墓参り ◎継承者 ◎永代供養 |
◎生前墓 ◎無縁仏 ◎寺院墓地 ◎納骨堂 ◎お墓と税金 |
お墓の歴史
亡くなった人をお墓に埋葬する歴史は古く、日本各地に残されている古墳に見られるように、古代から始まっています。しかし、古墳は天皇をはじめとする支配者階級の人に限られていました。一般的には、死後は土に還すという意味合いから、遺体がそのまま放置される風葬や遺棄葬が中心でした。平安時代になって仏教の普及に伴い、上層階級には火葬にして骨を埋葬する風習が広がりますが、庶民は土葬が主で、まだ遺棄葬にすることもあったようです。やがて、庶民にも仏教が浸透するようになり、江戸時代になると檀家制度が確立されます。お寺との結びつきが強くなり、一般庶民も墓を建てるようになってきました。 最初は遺骸を木棺や桶に入れて土葬した上に霊魂を封じ込めることを目的として土饅頭を築いたり、石を置いたり、常磐木を立てたりというようなものでした。武士階級では、板塔婆とか石塔婆などを建て、これが近世の卒塔婆や石の墓標の原型ともいわれています。一般庶民にも石の墓標が建てられるようになり、最初は一人一基の個人墓がふつうでしたが、大正時代から昭和時代初期にかけて、墓地不足などの理由から庶民も土葬から火葬へと移行し、「○○家之墓」というような今日のスタイルになってきたのです。
最初は遺骸を木棺や桶に入れて土葬した上に霊魂を封じ込めることを目的として土饅頭を築いたり、石を置いたり、常磐木を立てたりというようなものでした。武士階級では、板塔婆とか石塔婆などを建て、これが近世の卒塔婆や石の墓標の原型ともいわれています。一般庶民にも石の墓標が建てられるようになり、最初は一人一基の個人墓がふつうでしたが、大正時代から昭和時代初期にかけて、墓地不足などの理由から庶民も土葬から火葬へと移行し、「○○家之墓」というような今日のスタイルになってきたのです。
現在のお墓
大正時代から昭和時代の初めにかけ、都市に人が集中するようになると従来の寺院墓地や公営墓地だけでは墓地が不足し、広大な敷地に整然と区画整理された公園墓地が出現します。緑や草花が彩る閑静な公園の墓地は、死後の安らかな眠りが約束されたようで関心の高い墓地です。墓地不足がますます深刻化する現在では、民営の墓地が増え始め屋内墓所、納骨堂、地下式霊園などの新しい形態が登場。お墓事情が様変わりしています。お墓を建てる時期
お墓は最後にたどりつく安住の地です。死後の早い時期にお墓を建てるのが望ましいのですが、法律的には「墓地として都道府県知事の許可を受けた地域の土の中に葬る」を守れば、建てる時期に制限はありません。多くの場合は開眼供養に親族が集まることを考慮して、四十九日や百か日忌、一周忌などの命日に建てるようです。また、墓地不足や経済的事情などですぐにはお墓を取得できない場合は、遺骨を菩提寺や納骨堂に預けたり、自宅の仏壇に安置しておきます。さらに、墓地を取得したものの、すぐにはお墓が建てられない場合は、とりあえずは遺骨を納めるカロート(納骨棺)だけを作って埋骨を済ませて、卒塔婆や墓標を建てて供養します。お墓参り
 お墓は建てただけで終わりではなく、お参りして供養することが大切です。命日や忌日、お盆、お彼岸などにはお墓参りをします。お墓参りには、線香、供花、ローソク、供え物、手桶、ひしゃく、掃除用具などを持参します。手桶やひしゃく、掃除用具などは墓地で用意されていることもあります。お墓を訪れたらお墓の周囲を掃き清め、たわしなどで墓石の汚れを落とし、新しい水を墓石にかけます。水鉢の水を新しくして持参した花や供え物を供え、束の線香やローソクに火をつけて合掌します。供え物は故人の好物や季節の果物、お菓子などを用意し、お参り後は持ち帰ります。線香やローソクの火の確認も忘れないようにしましょう。
お墓は建てただけで終わりではなく、お参りして供養することが大切です。命日や忌日、お盆、お彼岸などにはお墓参りをします。お墓参りには、線香、供花、ローソク、供え物、手桶、ひしゃく、掃除用具などを持参します。手桶やひしゃく、掃除用具などは墓地で用意されていることもあります。お墓を訪れたらお墓の周囲を掃き清め、たわしなどで墓石の汚れを落とし、新しい水を墓石にかけます。水鉢の水を新しくして持参した花や供え物を供え、束の線香やローソクに火をつけて合掌します。供え物は故人の好物や季節の果物、お菓子などを用意し、お参り後は持ち帰ります。線香やローソクの火の確認も忘れないようにしましょう。このようにお墓に水をかけたり、線香を供えるのは意味があります。水は清めるだけでなく、あの世で飢えの苦しみから救うために清浄な水をささげるというもの。また、線香は異臭を消して空気を清浄にすることに加えて、故人の食べ物となる大切なものです。(インドでは死後は香を食べると信じられていた。)
継承者
お墓の使用権は、管理料を払い続ける限り永久的なものです。この権利は代々子孫に受け継がれていき、お墓を受け継ぐ人を「承継者」と呼びます。民法第八九七条では「系譜・祭具及び墳墓の所有権は・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が、これを承継する。但し、被相続人の指定があるときは、その者が、これを承継する」と規定されています。お墓の継承は墓地の永代使用権と墓石などの所有権を受け継ぐことであり、他人に譲渡することはできません。多くの墓地や霊園では正当な相続人(東京都では六親等内の血族、三親等以内の姻族)以外への使用権の譲渡は認められていないようです。
承継の手続きには名義変更が必要で、故人との関係を示す書類として承継者の戸籍謄本と住民票、故人の除籍謄本などを用意します。また、公営墓地の場合は、お墓の姓と承継者の姓が異なっていると使用権は承継できません。
女性の場合、婚家の姓のままでは実家のお墓を守ることができなくなってしまうのです。このような時には、婚家の姓を刻んだ新しい墓石を建てる(新しい契約になるので、永代使用料を払うことになります。あるいは継続とみなされることもあるので確認が必要)、永代供養墓にするなどの方法があります。
生前墓
最近、墓地不足の深刻化や"死"を身近な問題として考える人が多くなり、生前に墓を建てる人が増えています。これを寿陵と呼び、長生きできる墓とか縁起の良い墓ともいわれ、慶事として扱われるのです。寿陵には、戒名の字を朱書きにする習わしがあり、亡くなったら墨を入れ、朱を消します。寿陵の増加により、対応してくれるところは増えていますが、霊園によっては、遺骨がないとお墓が建てられない場合もありますので、事前に確認が必要です。永代供養
承継者が途絶えたり、海外へ移住したりと供養ができなくなる場合には、菩提寺に永代供養を依頼します。永代供養とは、菩提寺が特定の故人や先祖代々を永代に渡り供養することを意味し、永代供養料が必要です。また、檀家信徒以外でも永代供養の生前予約を受け付ける寺院墓地も増えてきていますが、寺院の永代供養には期限が決められていることもあるので、注意が必要です。
公営、民営の霊園では、一般に永代供養を受け付けていません。最近では、承継者がいなくても永久に供養してくれる共同型合同葬墓、つまり永代供養墓が各地に登場しています。これは慰霊碑や供養塔などのある共同納骨堂のような形式ですが、納骨の方法は全部の遺骨が合葬されるタイプ、一定期間は個別の骨壺ごとに安置され、その後に合葬されるタイプ、永久的に個人、夫婦単位のお墓として供養されるタイプなどに分かれています。
この永代供養墓の管理は民営や寺院墓地、市民団体などですが、平成10年に東京の小平霊園で共同型合葬墓が完成し、遺骨がなくても生前に申し込める制度を採用するなど、公営墓地でも検討されているようです。しかし、まだ試み段階の永代供養墓ですから、法律や規制がないのが現状。跡継ぎがいない、先祖代々のお墓には入りたくないなどと永代供養墓を希望する場合は、契約内容や条件を十分に確認するなど、選択は慎重にしたいものです。
無縁仏
お墓を供養する承継者が途絶えたり、不明になった場合は無縁墓になってしまいます。無縁墓と認定されたお墓の遺骨は納骨室から取り出され、墓地内にある慰霊碑や供養塔などに改葬されて供養されます。この場合、墓地の使用権は消滅します。法律による無縁墓の認定には、次のような手順が行われます。実際には、各地の墓地や霊園がそれぞれの定義を決めて、無縁墓を設定しているようです。
① 長い期間、お参りされていないお墓に、持ち主や縁故者を捜す札がかけられる。
② 連絡がない場合は、墓地の使用者や埋葬されている故人の本籍地、住所の市町村に対して縁故者の有無を確認する。
③ 縁故者が確認できないときは、墓地の縁故者を捜す公告を2種類以上の全国紙に3回以上掲載する。
④ 最後の公告から2ヶ月以内に申し出がない場合は、承継者がいないとみなされ、無縁墓と認定される。
寺院墓地
従来はお寺の境内や小規模の共同墓地という形でしたが、墓地需要が増えて郊外に新しい墓地を造成する寺も増えています。寺院墓地は、基本的に檀家制度で成り立っているので、資格が厳しく、その寺の檀家か、同じ宗派の信者以外は埋葬できません。改宗したり、新たに檀家になるには、入檀料が必要になります。寺院墓地のメリットは管理面で安心できることに加えて、法要などもスムーズに行えます。納骨堂
地、埋葬などに関する法律では「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」が納骨堂です。これは大寺院や霊園などに設置され、墓地不足の深刻化により、公営民営を問わず利用率が高まっています。納骨には、永代納骨とお墓を建てるまでの仮納骨があります。形はロッカー形式の簡単なものから霊檀などを設けた豪華なものなどさまざまで、使用料もお墓を建てるよりは安いものの種類によって異なります。お墓と税金
土地や住宅を購入した場合には「不動産取得税」「固定資産税」が発生しますが、墓地や霊園を取得した場合には、登記の必要がなく非課税扱いになります。その理由として土地の所有権は墓地や霊園にあり、永代使用の権利を取得しただけだからです。また、お墓を相続した時も「祭祀財産」の継承になり、祭祀財産は相続財産に含まれないので相続税の対象にはなりません。それゆえ、生前に寿陵を取得しておけば、その分相続財産が少なくなり、節税対策になります。
こうした税制のメリットに加えて、経済的にゆとりのある時期にお墓を用意しておくと、気持ちの上でも充足感が得られるなどの理由から、生前にお墓を購入する人が増えてきているようです。