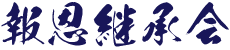ご先祖様の恩を感じ、先祖供養・お墓参りをしましょう
|
一般社団法人 日本生活助力協会 mail:houon@jstm.or.jp |

| ◎葬儀の種類 ◎葬儀と告別式の違い ◎告別式の服装 ◎通夜、葬儀、告別式への参列 |
◎葬儀、告別式の費用 ◎謝礼とお礼 ◎葬儀と相続 |
葬儀の種類
時代とともに、葬儀のかたちも多様化しています。遺族・親族の方々の想いや事情にもよりますが、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で選ぶ事が重要です。こちらでは、主な葬儀の種類をご紹介いたします。
| 葬儀の特性 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 一般葬 | 家族や親族以外にも、知人・友人、会社関係者やご近所の方なども参列する一般的な葬儀 | ・多くの方に一度に見送ってもらえる ・葬儀後の弔問対応が軽減できる ・香典収入が多い |
・参列者の対応に追われてしまう ・ゆっくりお別れができない ・参列人数により、飲食費などに無駄が出ることがある |
| 家族葬 | 親族や親しい友人・知人だけで見送る葬儀 | ・お別れの時間をゆっくりと過ごすことできる ・参列者の対応に追われない |
・葬儀後に、自宅への個別弔問が多発する恐れがあり対応に追われる ・周囲からの理解が得られない場合がある ・香典収入が少なくなる |
| 密葬 | 家族や近親者だけで葬儀を行い、後日一般参列者を招いた本葬を行う(本葬を行わない場合もある) | ||
| 一日葬 | 通夜を行わず、葬儀・告別式のみを1日で行う葬儀 | ・費用が抑えられる ・遺族への身体的、肉体的な負担が軽減される |
・日程の関係で参列出来ない人がいる ・前日から準備を行うので、式場費が2日分かかってしまう |
| 直葬 | 通夜や告別式を行わずに火葬のみを行う葬儀 | ・費用が抑えられる ・時間が軽減できる |
.気持ちの整理がつかない .菩提寺に、納骨を拒否される場合がある |
葬儀と告別式の違い
・葬儀は遺族が故人の冥福を祈り葬る儀式をさしますが、告別式は故人と親交があった人が死者に最後の別れを告げる儀式のことを言い、この2つは厳密には異なるものです。・最近は告別式と葬儀を一緒に行う場合が多くなっており、葬儀のあとで、「故人の冥福や成仏を祈る儀式」と、故人と最後のお別れをする「告別式」の両方を続けてとり行うという構成になっています。
例えば仏式であれば、僧侶による読経を中心とし、故人の成仏を祈る葬式に続いて、故人と生前おつき合いがあった人が故人に最後のお別れをする告別式を行うという流れです。
・最近では葬儀を密葬で行い、お別れの会や告別式だけが別の日に行われることもあります。葬儀だけを近親者だけで済ませて別途告別式を催す際には告別式を「お別れの会」などと呼んで区別したり、日を改めて行ったりします。
また、暦が友引の日には葬儀・告別式は行わないというのが一般的です。通夜は友引きでも行われます。
告別式の服装
告別式の服装は、基本的には葬儀の服装に準じます。通夜のように「予期せぬ訃報に、取るものもとりあえず駆けつけた」という場合には許される服装も、告別式では失礼にあたります。マナー違反とならないように注意しましょう。喪服での出席が基本となります。光るもの、派手なものは小物であってもNGです。
通夜、葬儀、告別式への参列
[親族・親戚]・故人と同居の親族は喪主と共に通夜、葬儀、告別式をとりおこないます。
一般的には、親族.親戚は通夜から葬儀、告別式へとすべてに出席します。
但し、ふだんから全く付き合いのない親戚や、遠戚 の場合であれば告別式だけに出席すれば良いでしょう。
[会社関係・職場]
・故人と親しい場合、あるいは特に世話になった場合、あるいは故人の直属の上司は、通夜、葬儀、告別式に出席します。
・故人の勤務先の代表者は、可能なら通夜と告別式の両方に出席します。
・上記以外の会社関係者は、告別式にのみ出席するか、あるいは代表者名で弔電を送ったり、連名で香典を出し、代表者のみ告別式に参列したりします。
葬儀、告別式の費用
葬儀の費用は、地域による格差が大きいことが知られています。葬儀一式と、寺院への費用、飲食接待費をすべて合計したお葬式に関わる総費用の全国平均は約240万円弱です。詳しくは地元の葬儀社にお尋ね下さい。
■葬儀費用の明細
葬儀の費用は値切りにくいとか、親族や参列者の手前、あまり安いものにはできないとか、いろいろと聞きます。しかし葬儀は費用だけをかければ良いというものではないと思います。故人の冥福を祈る、心のこもったものであれば無理をする必要はありません。
葬儀社と良く相談し、「これとこれは不要」「この部分はできる限りのことをしてあげたい」等、納得のいくプランをたててください。
ここでご紹介するのは葬儀費用の明細の目安です。
それぞれの費用が妥当な金額か、そして本当に必要なものかどうかを決める際の参考になさって下さい。
■主な葬儀費用の目安 (平成15年)
お葬式に関わる費用の明細をご紹介します。
下記はほんの一例です。地域、宗派、葬儀社により異なります。
ご遺族間でよく話し合い、 葬儀社とも相談し決めてください。
※葬儀一式という見積の場合は、斎場費、火葬料、車両(寝台車、霊柩車、マイクロバス等)が含まれていない場合があり、パック料金で安いようでも、あとで周辺費用が追加請求されてビックリすることがあります。御葬儀費用の明細は見積り時に必ず確認されることをおすすめします。
*祭壇 300,000円~ かなり高額なものまで
*棺 15,000円~ かなり高額なものまで
*お花 7,000円~
*遺影 12,000円~
*骨壷 17,000円~ かなり高額なものまで
*位牌 420円~
*枕飾り 15,000円~
*ドライアイス @8,400円/日~
*案内看板 15,000円~
*受付セット 10,000円~
*司会者 通夜~告別式までで50,000円~
*通夜振る舞い/料理 @2,000~@3,000円/人 ※飲み物代は別
*遺体搬送車(寝台車) 基本料金9500円+
・10KMまで2,730円
・20KMまで4,860円
・30KMまで7,800円
※上記に葬儀社の手数料が加算される
*斎場費・会場費 公営/50,000~100,000円
*民営/200,000円~ かなり高額なものまで
*霊柩車 25,000円~(距離による)
*火葬手配・火葬料 公営/0~30,000+葬儀社の手配料
*民営/50,000円~+葬儀社の手配料
*火葬場への送迎車・バス等 50,000円以上
*精進落とし/料理 @3,000~@5,000円/人 ※飲み物代は別
*お返し品 @1,000~@5,000円/人
*会葬礼状 基本料金+枚数単価 台紙と原稿により異なる。トータルで、 だいたい数千円
*御葬儀に関わるその他の費用(心づけなど)
・世話役さんには@5,000~10,000円
・ご近所のお手伝いの方には@2,000~3,000円
■葬儀費用の負担
・葬儀費用を遺族のうち誰が負担するのかについては、法律上の決まりはありません。一般 的には、通夜や葬儀に寄せられた香典には突然の出費に対する相互扶助の役割がありますので、葬儀費用を香典から支払い、不足する分があれば遺族で話し合って支払うことになります。
なお、遺産を相続した場合には、葬儀費用を支払った人は、相続税の申告の際に控除される費用があります(控除の対象となる費用が定められています。必ず葬儀費用の内訳、明細が必要となります)
謝礼とお礼
謝礼とは、感謝の気持ちを表わすための言葉や贈り物(金銭や品物)を言います。お礼も、謝礼とほぼ同様の意味ですが、謝礼の「謝」という語には、お礼の意味の他に「謝る」「金品」の意味が含まれるのに対し、お礼の「礼」という語にはお礼の意味の他に「礼儀・規範」「敬意」「儀式」の意味が含まれます。
こうしたことから言葉や手紙を通して感謝の気持ちを伝える場合には「謝礼」よりも、礼儀や敬意のこもった「お礼(御礼)」という単語の方が,よりしっくりくるということがおわかりいただけると思います。
■通夜・葬儀と謝礼、お礼、謝礼金
通夜・葬儀は突然に行われる場合が多いため、多くの人にお世話になる儀式だと言えます。
参列者、会葬者に対してはお礼・お返しを。
喪主側のお手伝いをして下さった方には謝礼・お礼をします。
■葬儀・告別式の司会者に謝礼・お礼・謝礼金
・葬儀・告別式の司会者に対し、謝礼は必ずしも渡さなくてはならないというものではありません。
通常は司会者のギャラも葬儀一式の料金に含まれています。しかし、専門の司会者ともなると、遺族の話をもとに、故人が生きてきた人生を深く掘り下げ、その生きざまを熱く紹介して下さる言葉の力にはまさに心を打たれるものがありますので、ぜひともお礼をしたいという場合もあるでしょう。
・基本的には心づけは、いちばん最初に「本日はお世話になります」という形でお渡しするものですが、謝礼であれば、「お世話になりました」という気持ちを込めて、後で渡しても良いでしょう。お渡しする場合には、数千円~2万円くらいで良いと思います。白い封筒に入れてお渡しします。
表書きはなしでも構いませんが、「御礼」などと書いても良いでしょう。下段は喪主の姓を書きます。
■通夜・葬儀の時にお世話になった近所の人に謝礼・お礼・謝礼金
・通夜・葬儀・告別式でお世話になった近所の方達にもお礼をします。簡単なお礼の品を持って初七日までに「おかげさまで無事に葬儀を済ませることができました」と、遺族がご挨拶に伺います。
持参する品については、菓子折りまたは実用品で、1,000~3,000円くらいまでのもので良いでしょう。
葬儀社のほうで、サンプルを用意している場合もありますので、相談すると良いと思います。
・白封筒でも良いですし、のしをつける場合は不祝儀の結び切りの熨斗で、表書きは「御礼」、下段には喪主の姓を書きます。「寸志」という表書きも用いることがありますがは目下の人あてにしか使えませんので注意して下さい。
■通夜・葬儀の受付係、会計係をはじめ世話役に謝礼・お礼・謝礼金
・初七日までには、受付係や、会計係などの各係をつとめてくれた方や、それらの係の取りまとめ役をして頂いた世話役の人にも、喪主または故人の配偶者がお礼のご挨拶に伺います。
持参する品については、菓子折りまたは実用品で3,000円~20,000円くらいまでのもので良いでしょう。社葬の場合には、会社にお礼に伺います。
葬儀社のほうで、サンプルを用意している場合もありますので、相談すると良いと思います。
・白封筒でも良いですし、 のしをつける場合は不祝儀の結び切りの熨斗で、表書きは「御礼」、下段には喪主の姓を書きます。「寸志」という表書きも用いることがありますがは目下の人あてにしか使えませんので注意して下さい。
■弔電を頂いたお礼
・弔電を頂いた方にはお礼状を出します。
「故◯◯◯◯儀 葬儀に際しましてはご多忙中にもかかわらずご鄭重な弔電を賜り厚く御礼申し上げます」など。
・お礼状はできるだけ早くお出しするのがコツです。
■通夜・葬儀に参列して頂いた方、香典などを頂戴した方にお礼・お返し
・葬儀に参列して頂いたら、お礼状(会葬礼状)はなるべく早く出しますが(郵送する場合もありますが、葬儀の際に渡す場合がほとんどです)、それとは別に香典や御供物を頂いた方にはお返しをします。このお返しを香典返しと言います。
・不祝儀の謝礼・お礼の、のしの表書としては「志」は宗教を問わず使われます。
その他には、宗教および地域により、のしの表書きが異なります。
■ハイヤーやマイクロバスの運転手、火葬場の作業員などに心づけ
・火葬場への移動に際し、心付けは渡さなくてはいけないと言うものではありませんが、地域によってはハイヤーやマイクロバスの運転手、火葬場の作業員などにも謝礼として手渡す慣例があります。
もし心付けを渡す場合は1,000円~5,000円くらい。白封筒に表書きは「御礼」。下段は、喪主の姓を書きます。
■寺院に謝礼・お礼
・寺院への謝礼は、葬儀・告別式の翌日に持参します。喪主(または故人の夫、または妻) が「おかげさまで滞りなく式を終えることができました。ありがとうございました。」とお礼を述べ、謝礼をお渡しします。謝礼を渡す場合の表書きは、御布施、御礼、戒名料で 結び切りの水引きの不祝儀熨斗袋、または白封筒。
・地方によっては、現金での謝礼だけでなく菓子折りも合わせて持参するところもあるようです。もしも菓子折りも持参する場合には、謝礼は菓子折りの上に乗せてお渡しします。
・やむを得ない事情で翌日お渡しするのが難しい場合には、葬儀・告別式の当日にお渡しします。
・僧侶にお布施を渡す時には、小盆の上に乗せ、表書きが僧侶からみて正面 にくるようにお渡しします。
・なお、遠方からおこし頂いた場合などは、謝礼の他に「お車代」も渡します。白封筒に入れ、金額は5,000~10,000円程度となります。
葬儀と相続
一般的な内容です。詳細については、法律の専門家や、税務署に確認することをおすすめします。■故人の相続財産、遺産(財産)を明確にする
すべての財産をリストにします。
現金、預貯金だけでなく、株券、土地、家屋などの不動産、貴金属、車両、故人の財産すべてが対象になります。 借金も相続対象となります。
■保険金を確認する
故人がその保険料の一部または全部を負担していた場合には、その死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金は相続税の課税対象となり、死亡保険金の受取人が相続人であった場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計が基準を超えると(非課税限度額を超える部分が)相続税の課税対象になります。
■遺言を確認する
遺言の有無と内容を確認します
■相続人を明確にする
相続人の範囲と順位を確認します。 相続権を放棄した人や、相続権を失った人を確認します。
遺産分割の協議の際には相続人の参加が必要となります
■相続人ごとに、相続額、相続税を計算する
相続税は、相続人ごとにいろいろな条件が加味されるために、相続人ごとに計算する必要があります。
なお、相続税の計算の際には、仮に喪主が葬儀の費用を負担したとしても相続人全員で負担したものとみなされますので、注意して下さい。
※法律の改正も含め、必ずご自身で最新の情報を確認して下さい。
[葬儀費用に関する控除]
葬儀に際して支払った費用の中で相続税の申告の際に控除される部分がありますので、明細を必ず用意しておいてください。
相続税を計算するときには、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます(下記)。
▼葬儀費用となるもの
(1)死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2)遺体や遺骨の回収にかかった費用
(3)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(4)葬式等の前後に生じた出費で通常葬式などに欠かせない費用(通夜等にかかった費用)
(5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
▼葬式費用に含まれないもの
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用
注1)包括受遺者とは、遺言により遺産の全部または何分のいくつというように遺産の全体に対する割 合で財産を与えられた人のことをいいます。
注2)ここでは、葬儀費用について紹介していますが、葬儀費用の他に遺産相続の際に差し引く事がで きる債務があります。詳細は国税庁のページでご確認下さい。
[相続税の申告書の提出期限]
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ケ月目の日です。